「NISAをやってるけど、成長投資枠って何?」
「どのファンドを選んだらいいかわからない…」
「そもそも、成長投資枠って使う必要あるの?」
もしあなたが、この中のどれか一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。
そして、最後の疑問への答えは、明確に「YES」です。 なぜなら、NISAの「成長投資枠」は、20代・30代が将来の資産を大きく育てるための『最強のエンジン』に他ならないからです。
とはいえ、強力なエンジンのアクセルの踏み方を知らなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
この記事では、あなたのそんな疑問や不安を完全に解消するため、以下の3つを解説していきます。
- 成長投資枠とは何か?(基本とポテンシャルの理解)
- 具体的なおすすめファンド5選(有力な選択肢の把握)
- 後悔しないためのファンドの選び方(あなた自身の正解を見つける公式)
この記事を読み終える頃には、あなたはもう迷いません。自信を持って成長投資枠というエンジンを始動させ、ご自身の資産を育てるための一歩を踏み出せるはずです。
NISAの成長投資枠とは?

2024年から始まった新NISAの成長投資枠について以下の3点を詳しく解説していきます。成長投資枠は将来に向けた資産作りには欠かせない仕組みです。しっかりと理解して資産形成を加速させましょう。
- NISAはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類に分かれる
- つみたて投資枠の対象商品を選べる
- 一括投資と積立投資を選べる
1.NISAはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類に分かれる
| 比較項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯非課税保有限度額 | 1,800万円(2つの枠の合計) | うち1,200万円まで |
| 対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した 一定の基準を満たす投資信託・ETF(金融庁の指定) | 上場株式、投資信託など (一部、高レバレッジ商品などを除く) |
| 投資方法 | 積立投資のみ | 一括投資と積立投資の両方が可能 |
| 主な使い方 | 毎月コツコツと安定的に資産形成の土台を築く | まとまった資金で投資したり、 幅広い商品から積極的にリターンを狙う |
新NISAは特徴の異なる2つの非課税枠を同時に使える制度です。具体的には、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象の「つみたて投資枠」(年間120万円)と、より幅広い投資信託や株式などが対象の「成長投資枠」(年間240万円)から構成されています。
生涯にわたる非課税保有限度額は合計で1,800万円ですが、そのうち成長投資枠で使える上限は1,200万円です。この2つの枠をどう組み合わせるかが、あなたの投資戦略の第一歩です。
2.つみたて投資枠の対象商品を選べる
結論から言うと、成長投資枠では、つみたて投資枠の対象となっている安定的なファンドも購入可能です。そのため、「成長投資枠だからハイリスクな商品を選ばないといけない」と考える必要は全くありません。
例えば、つみたて投資枠でS&P500に連動するファンドを積み立てつつ、ボーナスなどの臨時収入があった月に、同じファンドを成長投資枠で追加購入するといった柔軟な使い方ができます。選択肢が広いからこそ、基本に立ち返って安定的なファンドを選ぶのも、有効な戦略の一つだと覚えておきましょう。
3.一括投資と積立投資を選べる
成長投資枠の大きなメリットは、自分のタイミングで「一括投資」と「積立投資」のどちらも選べる点です。
まとまった資金がある場合は一括で投資して大きなリターンを狙うことも、毎月決まった額をコツコツ買い付けて購入価格を平準化させる(ドルコスト平均法)ことも可能です。例えば、相場が下がったと感じたタイミングで多めに買う、といった戦略も取れます。
ご自身の資金状況や相場観に合わせて投資スタイルを柔軟に変えられるのが、成長投資枠の大きな魅力と言えるでしょう。
NISA成長投資枠におすすめファンド5選

成長投資枠で投資できる商品は数多くあり、何を選べばよいか迷ってしまう方も多いはずです。そこで、特徴の異なる5つの人気ファンドをピックアップしてご紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の考え方や投資スタイルに合うファンドを見つけるための参考にしてください。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- FreeNEXT FANG+インデックス
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- 野村 グローバル・AI関連株式ファンド
1.eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| ファンド名 | リスク許容度 (目安) | 主な投資対象 | ファンド種別 | 手数料(信託報酬)の傾向 | つみたて投資枠とのバランス活用例 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 中 | 米国の主要大型株 約500社 | インデックス | 低い | つみたて投資枠のコア資産としつつ、成長投資枠でも買い増して米国株比率を高める。 |
低コストで米国を代表する約500社に分散投資できる、王道のインデックスファンドです。投資の神様ウォーレン・バフェット氏も推奨するS&P500指数に連動し、アップルやマイクロソフトといった世界的な大企業にこれ一本で投資できます。
特に、業界最低水準の運用コストを目指し続ける方針は、長期で資産を育てる30代の強い味方。何から始めるか迷ったら、まず検討したいファンドの筆頭と言えるでしょう。安定した土台を築きたい方におすすめです。
2.FreeNEXT FANG+インデックス
| ファンド名 | リスク許容度 (目安) | 主な投資対象 | ファンド種別 | 手数料(信託報酬)の傾向 | つみたて投資枠とのバランス活用例 |
| FreeNEXT FANG+インデックス | 高 | 米国の巨大テクノロジー企業 10社 | インデックス | やや高め | つみたて投資枠で安定的なファンドをコアとし、成長投資枠でリターンを狙うスパイスとして活用。 |
より積極的にリターンを狙いたいなら、米国の巨大テクノロジー企業10社に集中投資するこのファンドが選択肢になります。
構成銘柄は、Meta(旧Facebook)、Amazon、Netflix、Google(Alphabet)といった世界を牽引する巨大テック企業が中心です。大きな成長が期待できる反面、投資先が少ないため値動きは激しくなる傾向があるため、扱いには注意しなければなりません。
高いリスクを取ってでも大きなリターンを追求したい方や、自分のポートフォリオのスパイスとして少量組み入れたい方に向いている商品です。
3.SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
| ファンド名 | リスク許容度 (目安) | 主な投資対象 | ファンド種別 | 手数料(信託報酬)の傾向 | つみたて投資枠とのバランス活用例 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 中 | 米国の大型~小型株 約4,000社 | インデックス | 低い | S&P500と同様にコア資産に最適。「米国市場全体」に厚く投資したい場合に選択。 |
このファンドは、米国の大型株から小型株まで約4,000銘柄に投資し、米国株式市場全体の値上がりを狙えます。
S&P500が米国の主要企業約500社に投資するのに対し、こちらは将来大きく成長する可能性を秘めた中小企業まで含んでいる違いがあります。「特定の企業を選ぶのは難しいから、アメリカ経済全体にまるごと投資したい」という考えの方におすすめです。
eMAXIS Slimシリーズと同様に低コストな点も、長期投資において非常に魅力的です。
4.ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
| ファンド名 | リスク許容度 (目安) | 主な投資対象 | ファンド種別 | 手数料(信託報酬)の傾向 | つみたて投資枠とのバランス活用例 |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | やや高 | 米国ナスダックの主要100社 (ハイテク中心) | インデックス | 低い | つみたて投資枠でS&P500や全世界株式を選び、成長投資枠でハイテクセクターの比重を高めたい場合に組み合わせる。 |
米国のナスダック市場に上場する時価総額上位100社(金融を除く)への投資を目指すファンドです。
ナスダック市場には、情報技術(IT)やハイテク関連の企業が多く集まっています。そのため、構成銘柄もテクノロジー企業の比率が高く、時代のトレンドを捉えた成長性の高い企業群に投資できるのが特徴です。S&P500よりも、さらにIT分野に重点を置きたい場合に有力な選択肢となるでしょう。
こちらも比較的値動きは大きめなので、リスク許容度を考えた上で検討することが大切になります。
5.野村 グローバル・AI関連株式ファンド
| ファンド名 | リスク許容度 (目安) | 主な投資対象 | ファンド種別 | 手数料(信託報酬)の傾向 | つみたて投資枠とのバランス活用例 |
| 野村 グローバル・AI関連株式ファンド | 高 | 世界のAI(人工知能)関連企業 | インデックス | 高い | つみたて投資枠でインデックスの土台を築き、成長投資枠で特定のテーマ(AI)の将来性に期待して投資する。 |
これは、世界中のAI(人工知能)関連企業の株式に投資するアクティブファンドです。
インデックスファンドとは異なり、ファンドマネージャーが独自の調査に基づいて将来有望と判断した銘柄を選んで投資します。
AIという今後の大きな成長が期待されるテーマに特化しているのが魅力です。その分、信託報酬はインデックスファンドより高めに設定されていますが、市場平均を上回るリターンを期待できます。
特定のテーマの将来性を信じ、専門家の力に期待したい人向けの選択肢です。
NISA成長投資枠ファンドの選び方

おすすめファンドを見ても、結局どれが自分に合うのか判断するのは難しいと感じるかもしれません。ここからは、後悔しないファンド選びのために、ご自身で考えるべき5つのチェックポイントを解説します。この基準に沿って一つずつ確認していけば、数ある商品の中から自分だけの最適解を見つけ出すことができるはずです。
- 自分のリスク許容度を確認する
- 投資対象を確認する
- インデックスファンドとアクティブファンドの違いを把握する
- 運用成績や手数料を確認する
- つみたて投資枠のとのバランスを確認する
自分のリスク許容度を確認する
ファンド選びの第一歩は、自分がどの程度の価格変動(リスク)に耐えられるかを知ることです。
投資におけるリスクとは、危険性というより「値動きの振れ幅」を意味します。もし投資した資産の価値が一時的に30%下落したとき、冷静でいられるか想像してみてください。
30代は投資期間を長く取れるため、比較的高めのリスクを取れると言われますが、性格や家族構成によっても感じ方は変わります。自分の心の平穏を保てる範囲で投資することが、長く続けるための秘訣です。
投資対象を確認する
次に、そのファンドが「何に」「どの地域に」投資しているかを確認し、自分の考えと合っているかを見極めましょう。
投資対象は、交付目論見書などで詳しく確認できます。投資先は「全世界」なのか「米国」なのか、あるいは「先進国」か「新興国」か。また、株式だけでなく債券や不動産(REIT)に投資するタイプもあります。自分が応援したい国や、これから伸びると感じる分野に投資すると、モチベーションの維持にも繋がります。
あなたの考えに合ったファンドを選んでください。
インデックスファンドとアクティブファンドの違いを把握する
ファンドは大きく分けて「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2種類があります。この基本的な違いを理解することは非常に重要です。
インデックスファンドは、日経平均株価やS&P500といった市場の平均点(指数)を目指すため、運用コストが安いのが特徴。一方、アクティブファンドは専門家が銘柄を選び、市場平均を上回る成績を目指します。その分コストは高くなります。安定志向ならインデックス、専門家の目利きに期待するならアクティブ、というように自分の投資方針に合わせて選びましょう。
| 比較項目 | インデックスファンド | アクティブファンド |
| 運用目標 | 市場の平均点(日経平均株価、S&P500など)に連動する成果を目指す。 | 市場の平均点を上回る成果を目指す。 |
| 運用方法 | 指数に沿って機械的に銘柄を組み入れる。 | 運用の専門家(ファンドマネージャー)が独自の調査・分析で銘柄を選定する。 |
| 手数料(信託報酬) | 運用の手間が少ないため、低い傾向にある。 | 専門家による調査コストがかかるため、高い傾向にある。 |
| 値動きの傾向 | 市場全体とほぼ同じ値動きをする。(良くも悪くも「市場平均」となる) | 市場平均を上回る可能性がある一方、 下回るリスクもある。成果は運用者の手腕に左右される。 |
| こんな人におすすめ | 低コストで、市場の成長に合わせてコツコツ資産形成をしたい人。 | 手数料を払ってでも、市場平均以上のリターンを積極的に狙いたい人。 |
運用成績や手数料を確認する
長期的なリターンに大きく影響する「手数料(信託報酬)」と、過去の「運用成績(トータルリターン)」は必ずチェックすべき項目です。
特に信託報酬は、保有している間ずっと支払い続けるコスト。年率わずか数パーセントの違いでも、数十年後にはリターンに大きな差を生みます。
インデックスファンドであれば、同じ指数を目指す商品同士で手数料を比較するのが基本。アクティブファンドの場合は、手数料の高さを上回る運用成績を上げてきたか、という視点で確認することが大切です。
つみたて投資枠のとのバランスを確認する
最後に、成長投資枠だけで考えず、つみたて投資枠と合わせたポートフォリオ全体でバランスを見ることが重要になります。
例えば、つみたて投資枠で全世界株式のような安定的なファンドを選んでいるなら、成長投資枠では少しリスクを取って特定のテーマ株ファンドに挑戦する、といった戦略が考えられます。
2つの枠をうまく組み合わせることで、リスクをコントロールしながらリターンを狙う、自分だけの最適な資産配分を構築できる。これが新NISAを上手に活用するコツです。
自分の投資スタイルに合わせて成長投資枠を活用し資産を増やそう

結論として、NISAの成長投資枠はあなたの資産形成を加速させる強力なツールです。自由度が高い分、最初は戸惑うかもしれませんが、今回お伝えした選び方のポイントを押さえれば、自分に合ったファンドがきっと見つかります。
大切なのは、他人の意見に流されず、自分のリスク許容度や投資方針をしっかり見つめ直すこと。成長投資枠という制度を最大限に活用して、自分のペースで着実に未来の資産を育てていきましょう。
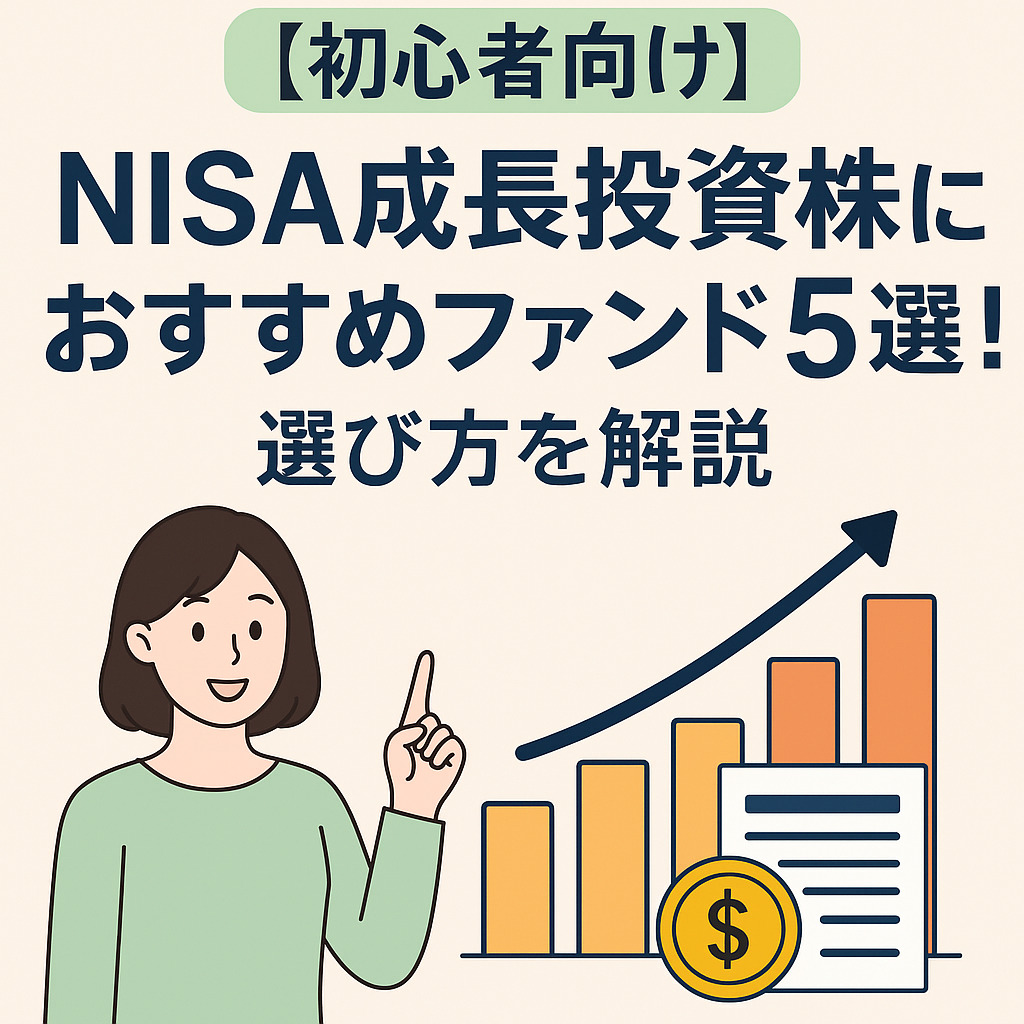

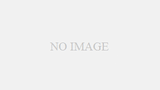
コメント